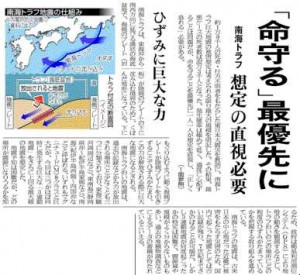新聞を教育に活用するNIEに、県教育庁も本腰を入れ始めた。所管する県総合教育センターで教員向けの研修講座を実施し、NIE全国大会にも教育庁職員2人を派遣。どちらも初めての取り組みだ。一方、現場では、この夏休みに小中高合わせて15校がNIEアドバイザーや新聞記者を講師に招き校内で研修している。関心が高まる現場を行政が後押しする格好で、今後、NIE活動に弾みがつきそうだ。(具志堅学)

NIEアドバイザーの佐久間洋・伊平屋小教諭(右から4人目)の指導で新聞を活用した実践に取り組む小学校の教員=7月27日、沖縄市与儀の県立総合教育センター
県教育庁の総合教育センターは7月末に小学校、8月初めに中学・高校の教員向けの講習会を開いた。それぞれ40人、24人が参加した。新聞記事に見出しを付けたり、切り離した記事を再構成する作業などを実践し、言語活動を重視するNIEの実践を体感。記事をもとに、にぎやかに意見交換する場面もあった。
参加者から「子どもに新聞に親しんでもらう方法が分かった」「楽しんで取り組むことができた」などの意見が寄せられた。
福井県で7月に開かれたNIE全国大会には最多の1780人が参加した。学校教育課の真栄田義光指導主事は「生徒の思考力・判断力を育むために新聞をうまく使っている。高校現場で取り組んできたことの教育効果も確認できた」と評価。生涯学習振興課は田畑武正班長を派遣し、ともに全国レベルの盛り上がりを体感したようだった。
中頭教育事務所は来年度、採用10年目の教員研修に取り入れたい考えで対象は70~80人を想定。学校現場に指導・助言する指導主事の研修に取り入れることも検討している。北谷町教委も研修を検討している。
一方、現場の取り組みも広がりを見せている。NIEアドバイザーは10校、本紙記者は5校の校内研にそれぞれ招かれた。本紙読者局・販売店が進める新聞スクラップ教室の参加者は、親子合わせて千人近くに上った。
大城浩教育長は、高校の教員として新聞を活用してきた自身の体験を踏まえ「子どもの社会性・感性を育むための最良の教材。学校・家庭・地域と連携して協力に取り組みたい」と新聞活用の効果を重視する。
行政主導で進められてきた全国と異なり、沖縄ではこれまで、教員が先行して取り組み、それに新聞社が協力する形だった。それだけに県教育庁などの動きは現場に活気を与えそうだ。