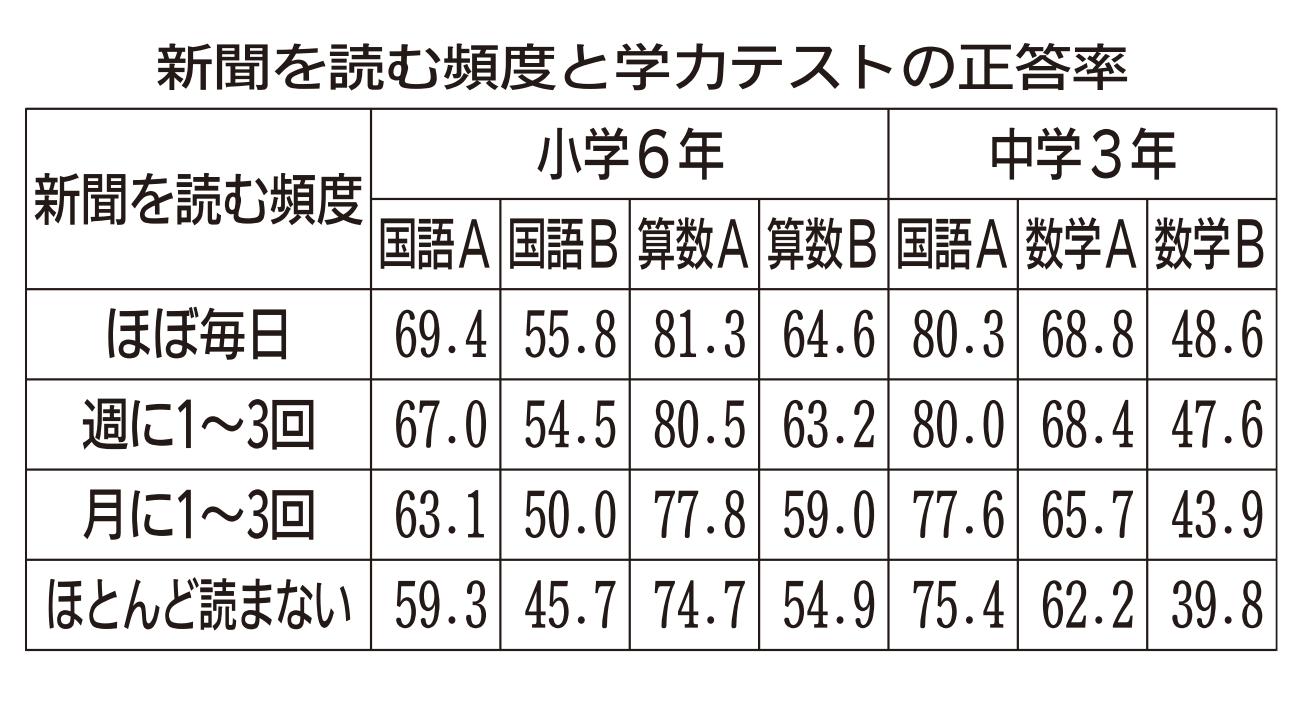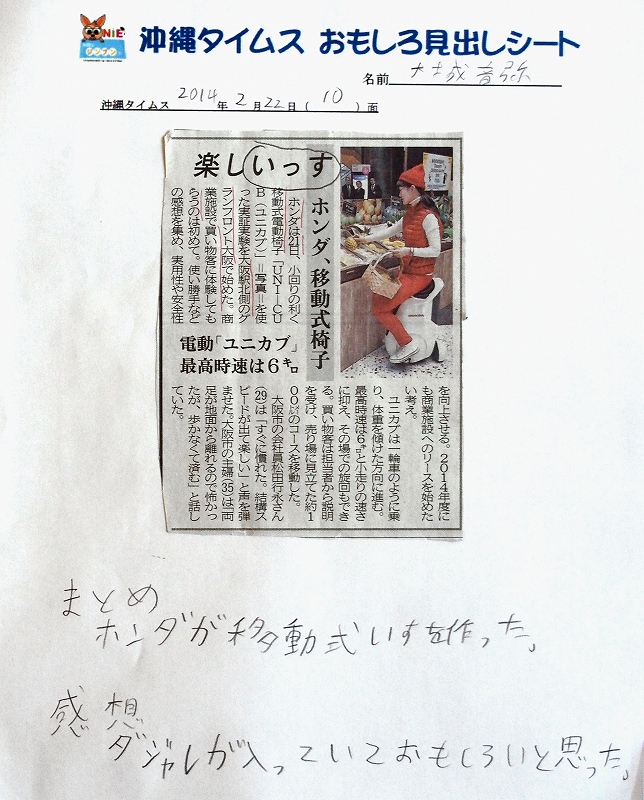NIE実践指定校の報告会(主催・県NIE推進協議会)が4日、那覇市久茂地のタイムスホールで開かれた。日本新聞協会指定と県推進協指定の計12校が発表、2校が紙面報告した。新聞を授業や朝の活動で継続的に使うことで読解力や意見などの表現力が高まっていることなどが紹介されたほか、教科内容に組み入れた例などが報告された。
知識を吸収し消化 新垣和哉教諭(喜瀬武原小中学校) NIEの効果を数字で図るのは難しいが、児童・生徒が変容していくのを体感できる。知識を吸収し、消化し、はき出せるようになる。引っ込み思案な子どもたちが、自分の考えをまとめ発信する機会をつくりたい。
NIEの効果を数字で図るのは難しいが、児童・生徒が変容していくのを体感できる。知識を吸収し、消化し、はき出せるようになる。引っ込み思案な子どもたちが、自分の考えをまとめ発信する機会をつくりたい。
当校は小学生30人、中学生14人。規模の小ささを生かし、小中合同で取り組んでいるのが特徴だ。関連性のある記事を選ぶ作業をさせると、たとえば小学生は水族館の入場者数と釣りの記事を結びつけることもある。その発想が面白い。逆に中学生のやり方や考え方を見て小学生が学ぶことも多い。
取り組み内容の掲示は、事務員や図書館司書が大いに動いてくれた。みんなを巻き込むことで、学校全体のNIE理解が深まる。
続けるうちに変化 當銘直美教諭(真喜屋小学校)
 3~5年生を中心に、新聞を活用している。3年生では「私が○○と思った写真」をテーマに、新聞から写真を選んでもらう授業をした。最初は「すごいと思ったもの」ばかりだったが、続けるうちに「心配だと思った写真」としてヤンバルクイナの事故記事を切り取ってきたり、「危ないと思ったもの」としてオスプレイが民家上空を飛行しているものを選んだりと、視点が変わってきた。
3~5年生を中心に、新聞を活用している。3年生では「私が○○と思った写真」をテーマに、新聞から写真を選んでもらう授業をした。最初は「すごいと思ったもの」ばかりだったが、続けるうちに「心配だと思った写真」としてヤンバルクイナの事故記事を切り取ってきたり、「危ないと思ったもの」としてオスプレイが民家上空を飛行しているものを選んだりと、視点が変わってきた。
1こまずつ切り離した4こま漫画を基に、意見を出し合う授業にも取り組んだ。子どもから、新聞でこんなに面白いことができると思わなかったとの声が出た。
新聞を身近に感じる児童が増えてきたが、NIEを日常化するため活用法の研究と具体化が不可欠と感じている。
学びと社会つながる 宮城良子教諭(右)高良真弓教諭(陽明高校) 新聞記事を活用することで、教科書で学んでいる単元と、社会とのつながりに気付いてもらうことができた。世界、沖縄の政治や経済を身近に感じ、自分なりの意見を持つこともできた。
新聞記事を活用することで、教科書で学んでいる単元と、社会とのつながりに気付いてもらうことができた。世界、沖縄の政治や経済を身近に感じ、自分なりの意見を持つこともできた。
政治経済の授業では、単元ごとに関連する記事を取り入れている。新聞から質問を出したプリントを作成し、意見も書いてもらう。定期試験でも、必ず新聞から出題。切り抜いた記事を基に、生徒それぞれが選ぶ「十大ニュース」も発表してもらった。
保健体育の授業でも、健康や環境などの分野で興味のある記事を選んでもらった。グループ内で発表し、友人同士で情報を教え合っている。今後は情報が偏らないよう、さまざまな記事を提供していきたい。
意見交換が活発化 石川美穂教諭(興南中学校) 全学年の国語で、「新聞リレー」に取り組んだ。気になる記事とともになぜその記事を選んだかや、気付いてほしい点を書き、次の生徒がそれに答えていくというもの。生徒間の意見交換が活発になり、想像以上の効果があった。
全学年の国語で、「新聞リレー」に取り組んだ。気になる記事とともになぜその記事を選んだかや、気付いてほしい点を書き、次の生徒がそれに答えていくというもの。生徒間の意見交換が活発になり、想像以上の効果があった。
毎日の宿題として、四季や伝統行事などへの理解を深める、コラムを使ったワークシートも取り入れた。
東京五輪の開催が決まった時には、各社が出した号外を読み比べ。見出しの違いを見ながら、読み手に伝わる印象の違いを考えた。
NIEを始めて、生徒たちの国語力は伸びてきている。一定の成果があるが、今後はさらに効果を見据えた取り組みが必要。NIEを広げる上でも、欠かせないことだと思う。
きらりアイデア(ほかの実践校の事例)
小禄南小学校…児童の作品を保管し、異動してきた教師と共有。
伊野田小学校…地域の人も利用できる新聞コーナーを設置。
浜川小学校…全学年で週1回朝のNIEタイム。読み聞かせなど。
中原小学校…3年生が同じ部首の漢字探し。教科書では文字が少ない。
越来小学校…毎週末親子でスクラップ。会話弾む(4年生)。
沖縄アミークスインターナショナル…4こま漫画を壁一面に掲示。まず関心を高める。
宮良小学校…見出しだけ切り抜き。「短くても伝わる」(5年)。
コザ小学校…委員会活動を取材し、伝えたいことを見出しに(5年)。
伊平屋小学校…1年生も授業参観日に親子で切り抜き新聞作り。
沖縄工業高校…琉球・沖縄史を記事で学ぶ。資料集には記述少ない。