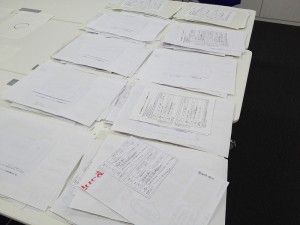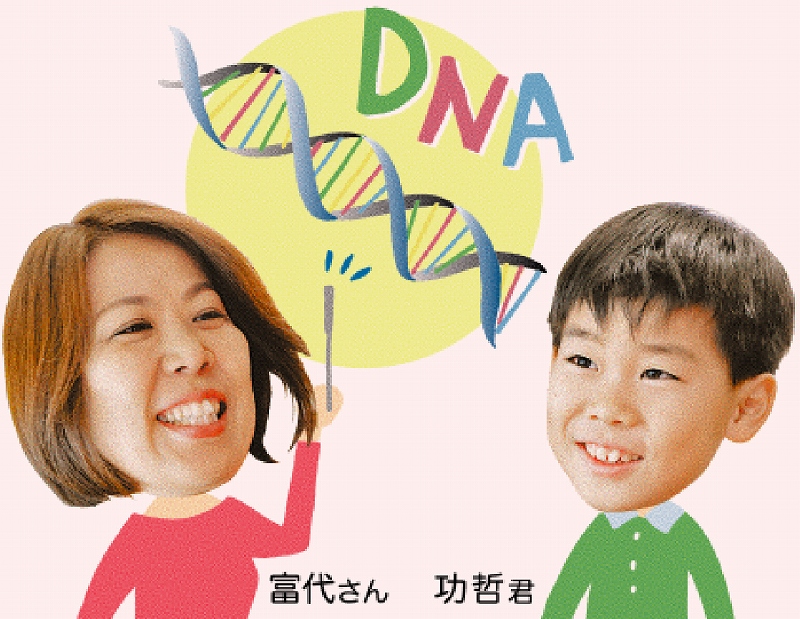日本NIE学会第10回愛知大会が23日、名古屋市で始まった。「真価問われるデジタル時代のNIE」と題したシンポジウムでは、社会を形作る議論の土俵の役割を新聞が果たし、学校で活用するという意義が語られた。
教職員や研究者、学生、新聞社員など250人余りが参加し、2日間にわたって研究発表や討議を行う。
シンポジウムは、多くの情報源がある中で新聞の存在感が薄れているとの現状認識から今後の方向性を探った。
ジャーナリストの大谷昭宏さんは「議論のある社会が強い社会。議論を起こすのが新聞の役割」と指摘。関連して、タレントの春香クリスティーンさんは出身地のスイスでは、大人も子どもも読んでいたと話し「授業で新聞を使うことはなかったが、休み時間に友達と共通のものを読んでディスカッションできた。日本でそんな場がまったくないのがさみしい」と話した。