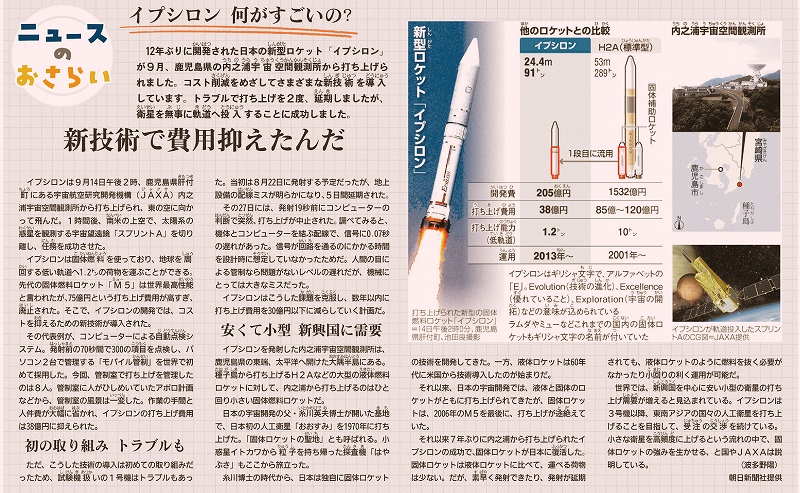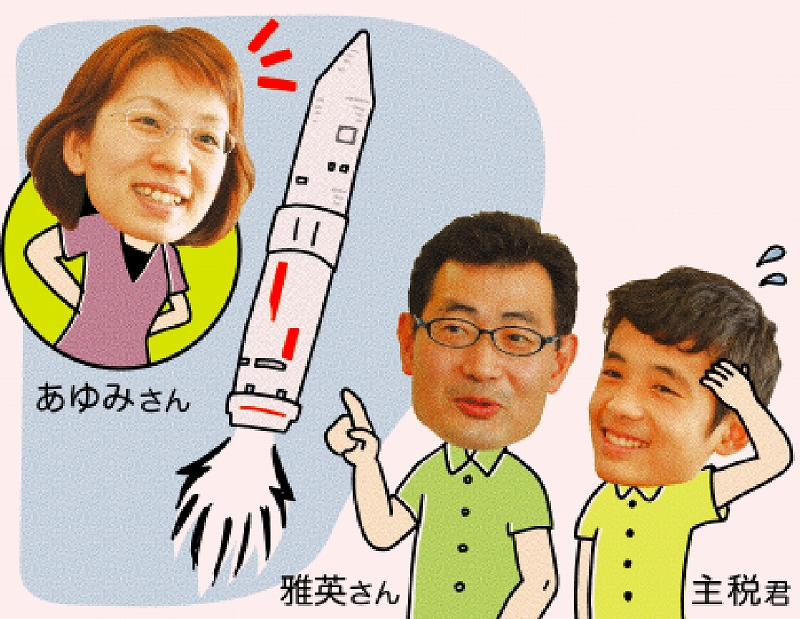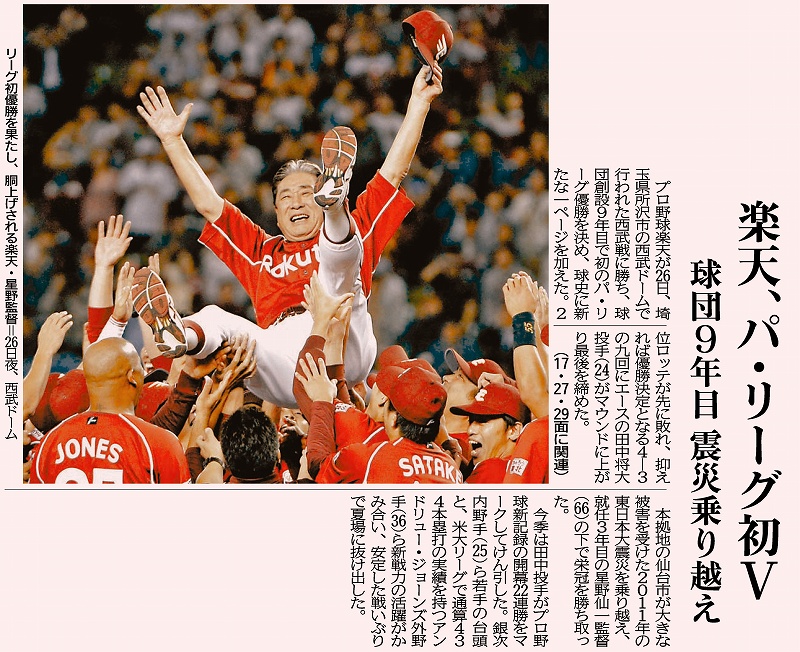那覇市立石田中学校3年3組の学級PTAが12日、新聞講座を開き、沖縄タイムスNIE事業推進室の指導で、気になった記事を紹介し合ったり、見出しになった言葉を本文から探すなど新聞の読み方や楽しみ方を学んだ。
生徒30人余と保護者6人が参加。見出しを頼りに10分間で全ページに目を通し、その後気になる記事を一つ選んでグループで紹介し合った。読んだ感想を五・七・五調で書き出すワークショップも実施した。
福里翔丸君は「学級レクなのに新聞ってビミョウと思ったけど、やってみたら面白い記事も見つかった。選んだ記事について人の意見が聞けて面白かった」。
担任の宮里征吾教諭は「普段より思っていることを活発に話していた」と記事を仲立ちにした話し合いを振り返った。保護者も「部活動その情熱で学業も」と五・七・五調でまとめ楽しんでいた。企画した学級PTA委員長の真栄田明さんは「新聞とは一生の付き合いになる。読み方を身につければよい習慣になる」と長い目で効果に期待した。