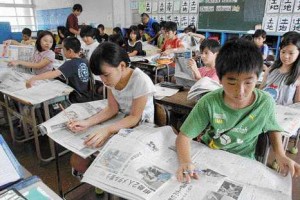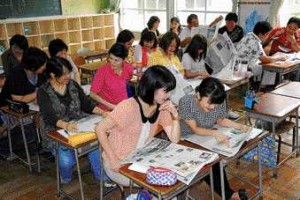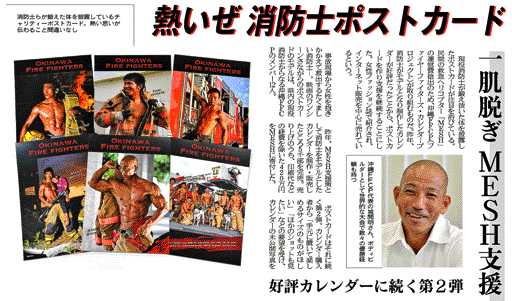上陸で問題になっているね
外国は何で文句言うのかな
尖閣諸島など領土をめぐる問題が次々に起こっています。島袋敦也君(14)と久仁人さん(49)親子も深刻な問題だと感じています。
久仁人さん▶敦也、尖閣諸島の魚釣島で何が起こっているか知ってる?
敦也君▶この島は自分たちのものとか言って中国人が上陸したんでしょ。
久仁人さん▶そう。今度は日本人が上陸して問題になっている。
敦也君▶日本人の所有者がいるって。東京都が購入するとか。だから日本の島なんでしょ。なんで外国から文句言われるのか。わからんなぁー。
 久仁人さん▶そもそも、この島を日本の領土と中国などが認めていた時期があった。でも、この島の周りには海底資源や海産資源が豊富だとわかった時から自分たちの島だと主張してきたらしいな。
久仁人さん▶そもそも、この島を日本の領土と中国などが認めていた時期があった。でも、この島の周りには海底資源や海産資源が豊富だとわかった時から自分たちの島だと主張してきたらしいな。
敦也君▶あー、日本はその時に海底資源を採っていればよかったんじゃないかな。時間空けてたから、こうなったのかも。
久仁人さん▶なるほど。騒ぎはしばらく続きそうだよ。