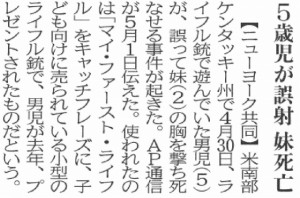沖縄タイムス社は5月から、編集局にNIE事業推進室を設置しました。紙面と事業運営の両輪で学校、家庭、地域の新聞活用を支援します。
日曜日の親子向け新聞「ワラビー」、月1回の「月刊NIE」(毎月最終水曜日)などの紙面づくりと、スクラップ教室・コンテストや児童・生徒、教師向けの出前授業、地域での新聞活用講座などの事業を行います。
お問い合わせはこちらから。
作成者アーカイブ: admin
学生結ぶ記事切り抜き 資格取得や授業に活用 沖国大で「しんぶんカフェ」
沖縄国際大学内に「沖国しんぶんCAFE」が4月に誕生した。ディベートや資格取得に向けた勉強などに生かそうと学生たちが足を運んでいる。新聞を切り抜き、自らの視点を付箋に書き込んで次に読む人にリレーするなど、独自の新聞活用法を展開している。(與那覇里子)
同カフェは、那覇市安里のコミュニティーカフェ「origin」で開かれている「しんぶんカフェ」の2号店。大学内の福祉・ボランティア支援室にあり、常時開放されていて、自由に利用できる。テーブルの上に、沖縄タイムス、毎日新聞、福祉新聞の3紙が置かれ、自由に読むことができる。新聞になじみのない学生に身近に感じてもらおうと、同室の職員や学生らが記事を切り抜き、貧困や福祉などのテーマごとの区分けもしている。
開設のきっかけは、同大3年の吉濱文佳さん(20)が、同室に常駐する経済環境研究所の稲垣暁特別研究員に「社会福祉士になるための勉強方法を知りたい」と相談したこと。稲垣研究員が「社会のニーズや現状を新聞でリアルに知ることで、学びもより深くなる」とアドバイスし、カフェの開設につながった。
吉濱さんは同室に通い、「後見」「ノーマライゼーション」など、記事で分からない言葉があれば、辞典などで調べて付箋に書き込み、記事に貼り付ける。「教科書を勉強するよりも社会の事情も分かるし、再編集することで、自分の実にもなっている」と効果を感じ始めている。他の人が付箋を貼った箇所を読んで勉強になることもある。
16日の昼休み。ゼミの授業で企画されているディベート大会の準備のために、約10人の学生たちがカフェに集まった。テーマは「生活保護費の削減」。貧困や高齢者の現状などが書かれた記事を読み込み、付箋に意見を書き込んで新聞に貼り付けた。
大城翔平さん(20)は、「カフェで新聞を読むことは考えるきっかけになる。読んで自分の視点を持てるようになることが大事」。喜友名朝也さん(21)は、「切り抜かれているので読みやすい。『奨学金』の記事が身近で考えさせられた」と語った。
幸地さんちのNIE(68)粟国に珍鳥85種続々
珍しい鳥が集まってるよ
気候がよく快適なのかも
粟国島に珍しい渡り鳥がたくさん来ています。幸地功哲君(10)と母親の富代さん(42)は、なぜ集まってきたのか考えてみました。
功哲君▶ウソ、コルリ、ミヤマヒタキ…
富代さん▶なに~? うそついたときのおまじない?
功哲君▶タイトル(見出し)を読んだんだよ! きれいでしょ。
富代さん▶わぁ。可愛いね~。鳥の名前だ。
功哲君▶「ウソ」って鳥の世界でうそつきなのかな。
富代さん▶青森では桜の芽を、このウソが好んで食べるんだって。珍しい鳥が沖縄に集まってるね。
功哲君▶海を渡って来たの?
富代さん▶5月なのに北海道では雪が降ったり、急に夏日になったり…。気候が原因かも。天気が安定しているのは、鳥にとっても過ごしやすいんじゃないかな。
功哲君▶そういえばスーサーが庭に来てるよね。こないだもキャベツについていたアオムシをつまんで飛んでいったの見たよ。
富代さん▶愛鳥週間だからってそんなにタイミング良く観察できたの?
功哲君▶ウソじゃないよ~!
[出前記者]取材のコツ学び 壁新聞を作ろう 港川小4年生
港川小学校(崎濱秀一校長)の4年生155人は16日、沖縄タイムス記者を講師に招いて新聞の仕組みや取材のこつを学んだ。近くの浅瀬についての壁新聞を作るための事前学習で、子どもたちは「分かったことを生かしていい新聞を作りたい」と取材や新聞制作に意欲をみせた。
講師は、社会部ワラビー担当の具志堅学記者が務め、児童はメモを取りながら聞き、取材の練習を兼ねた。
具志堅記者は「見出しは記事の一番大事なところを抜き出したもの」「取材の前に質問することをあらかじめ考える。分かるまで何度聞き直してもいいよ」などと話し、子どもたちは真剣な表情でメモを取っていた。
4年生は今後、近くの浜にある岩礁、通称・カーミージー周辺に出向いて生き物を観察したり、地元の人から話を聞いたりして壁新聞を作る。饒平名芽衣さんは「カーミージーの名前の由来などについて調べたい」と話した。
「新聞に興味持って」 宜野座小で本紙通信員が出前講座
児童にもっと新聞を知ってもらおうと、本島北部地域を取材する沖縄タイムスの仲地暁通信員(61)が10日、宜野座村立宜野座小学校(宮城司校長)で出前講座を行った。5年1組の児童に、紙面の構成や特徴などを説明した。
仲地通信員は「新聞を見ればきょうが何の日かよく分かる」と説明。10日付本紙1面記事について吉山凜君(10)は、愛鳥週間を報じるヤンバルクイナの写真が印象に残ったと発表。交通事故の増加を伝える記事に「朝、新聞を見てびっくりした。かわいそう」と話した。
仲地通信員は村出身で、これまでに漢那小校長を務めるなど地元に精通。村内の話題を伝えたこれまでの記事のスクラップをみせながら「みんなの住む宜野座の記事もたくさんの人たちに読まれている。新聞に興味をもってみよう」と話した。
與儀柊人君(10)は「新聞にはいろんな記事が書かれていることが分かった。また読みたくなった」と笑顔をみせた。
講座を終えた仲地通信員は「新聞のおもしろさをたくさんの子どもたちに知ってもらいたい。今後も活動を継続していきたい」と意欲をみせた。
教師ら新聞活用法学ぶ 第1回おきなわNIEセミナー
県NIE推進協議会(山内彰会長)の第1回おきなわNIEセミナーが11日、那覇市久茂地のタイムスビルであった。教員ら32人がNIEアドバイザーの助言を受け、学校での新聞の活用法を体験した。
メーン講師を務めた県立総合教育センター研究主事の甲斐崇アドバイザーは、毎週木曜日の朝の始業前に「NIEタイム」を始めた北谷町立浜川小学校が取り組む「新聞読み聞かせ」を紹介した。甲斐教諭は「発達段階に応じて記事を選ぶことが大事。朝の時間を使えば、教科に関係なくできる」と話した。
写真を選びコメントするワークショップもあり、知識を活用する力を育てるための道具として新聞を使い、継続して取り組むことの大切さを強調した。受講した読谷高校の齋藤綾教諭は「先生方と意見を交わして楽しかった。生徒たちにとっても新聞に興味を持ってもらう、良いきっかけになると思った」と話した。
上阪さんちのNIE(67)5歳児が誤射 妹死亡
子どもに銃が必要なの!?
日本はハサミでも大ごと
アメリカでまた、悲しい事件が起こりました。上阪主税君(13)と妹のきらりさん(12)は、銃社会の大変さを感じたようすです。
5歳児が誤射 妹死亡
■2013年5月3日国際面
【ニューヨーク共同】米南部ケンタッキー州で4月30日、ライフル銃で遊んでいた男児(5)が、誤って妹(2)の胸を撃ち死なせる事件が起きた。AP通信が5月1日伝えた。使われたのは「マイ・ファースト・ライフル」をキャッチフレーズに、子ども向けに売られている小型のライフル銃で、男児が去年、プレゼントされたものだという。
きらりさん▶これ見て。大変!
主税君▶僕もエアー銃を持っているけど、人や動物に向けて撃つことは厳しく禁止されているよ。
きらりさん▶なんで子どもに銃が要るの!
主税君▶男の子は武器や乗り物、強くて速いものが好きだから、欲しくなるんだよ。
きらりさん▶好きだからって、なんでも与えていいの?
主税君▶アメリカは銃社会で、自分の身を守るために必要らしいよ。1人1丁持っている計算だって。
きらりさん▶日本はどうなの?
主税君▶日本は銃刀法っていう法律があって、一般の人が銃を持つことはできません。
きらりさん▶オバマ大統領は対策を考えないと。学校に金属探知機があるのはおかしいよ。
主税君▶那覇空港でハサミが見つかって、1時間30分空港が閉鎖されたよね。学校でハサミが見つかったら授業は閉鎖されるのかな?
きらりさん▶授業が無くなるのはちょっとうらやましいね。