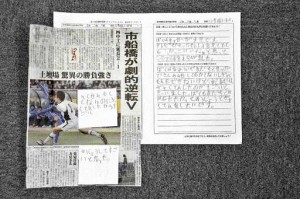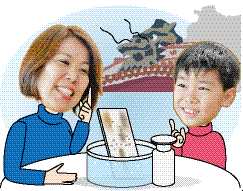鳥が衝突1メートルの穴すごい
無事着陸してよかったね
鳥が飛行機にぶつかったニュースに目を止めた島袋久仁人さん(48)。敦也君(13)と空の安全について語りました。
鳥衝突 機首に1メートルの穴
18日午後5時11分ごろ、第11管区海上保安(ほあん)本部那覇航空基地所属の航空機が東シナ海海上を警戒中、高度約300メートルの地点で鳥が機首部分に衝突し、機体が損傷した。飛行に影響はなく、約1時間後に目的地の石垣空港に着陸した。
 久仁人さん▶敦也、バードストライクって知ってる?
久仁人さん▶敦也、バードストライクって知ってる?
敦也君▶鳥が飛行機にぶつかることでしょ。
久仁人さん▶そうそう。飛行機に鳥がぶつかって、縦横1メートルの穴が開いたそうだ。
敦也君▶よく窓ガラスにあたらなかったよね。もしそうだったら、飛行機はどうなったんだろう? 無事に着陸できたんだろうか。
久仁人さん▶今回は無事だったんだけど。ぶつかった鳥の名はアホウドリで…。
敦也君▶えぇ? アホウドリ!? でも、鳥の方がかわいそう。だって、飛行機の方が断然速いでしょ。鳥に飛行機がぶつかってきたというのが本当じゃない。パイロットは鳥をさけて飛行できなかったのかな。
久仁人さん▶うーん。どうだろうね…。